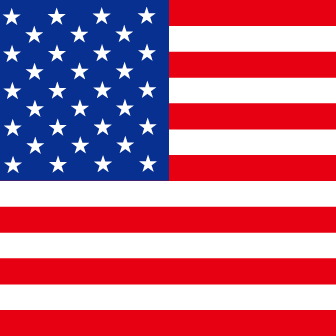[コラム]夏の集い、会話は弾んでいますか?~「ヒアリングフレイル」という新たな視点~
目次
【連載】聞こえの衰え、見過ごしていませんか?~ヒアリングフレイルを正しく知り、豊かな人生を~
第1回:夏の集い、会話は弾んでいますか?~「ヒアリングフレイル」という新たな視点~
8月に入り、夏本番。お盆の帰省や夏祭りで、久しぶりに家族や友人が集う機会も増える季節です。しかし、その賑やかな輪の中で、誰かの声が遠くに聞こえたり、話の内容がうまく掴めずに会話に入りづらさを感じたりしていませんか?あるいは、ご家族の誰かが、以前よりも口数が減り、少し寂しそうな表情を浮かべていることに気づいたかもしれません。その些細な「聞こえにくさ」は、単なる「年のせい」で片付けてはいけない、ご自身や大切な人の健康に関わる重要なサインかもしれません。
「ヒアリングフレイル」とは何か?
近年、医療や介護の現場で注目されている「ヒアリングフレイル」という言葉をご存知でしょうか。これは、単に聴力が低下する「難聴」という状態だけを指すものではありません。ヒアリングフレイルとは、聴覚機能の衰えが原因で、人とのコミュニケーションが難しくなり、その結果として生活の質(QOL)が低下したり、心身の活力全般が衰えたりする「フレイル(虚弱)」につながる一連の状態を指す、より包括的な概念です 。
すでに、山口県防府市や埼玉県入間市、東京都豊島区といった多くの地方自治体が、この「ヒアリングフレイル」という言葉を用いて、住民向けの健康啓発リーフレットを作成したり、相談窓口を設けたりしています 。これは、聞こえの問題がもはや個人の感覚の問題ではなく、地域社会全体で取り組むべき公的な健康課題であるという認識が広がっていることの証左と言えるでしょう。
なぜ「フレイル」なのか?―言葉の持つ意味
なぜ、あえて「難聴」ではなく「ヒアリングフレイル」と呼ぶのでしょうか。そこには重要な意味が込められています。「老人性難聴」という言葉には、どこか「加齢によるもので、避けることも元に戻すこともできない」という、ある種の諦めにも似た響きがあります。しかし、「フレイル」という言葉は、老年医学において「適切な介入によって進行を予防し、再び健常な状態に戻る可能性がある、可逆的な状態」として定義されています。
つまり、「ヒアリングフレイル」という言葉を用いることは、聞こえの問題を「仕方がない老化現象」から「予防や対策が可能な健康課題」へと捉え直す、意識の転換を促すための戦略的なアプローチなのです。これまでの受動的な諦めから、自らの健康を能動的に管理する姿勢へとシフトさせる。この前向きな視点こそが、ヒアリングフレイルという概念の最も重要な核心です。
この概念は、身体全体の衰えを示す「身体的フレイル」や、社会とのつながりが希薄になる「社会的フレイル」とも密接に関連しています 。聞こえの衰えは、単独で存在するのではなく、心身の健康全体を揺るがしかねない、老年期における健康ドミノの最初の一枚となり得るのです。