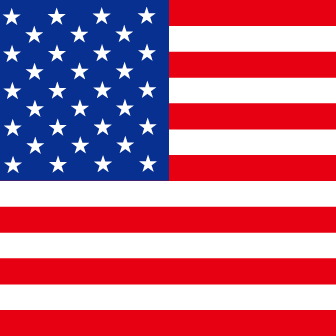[コラム]聞こえの低下が招く、社会的な孤立と孤独
目次
【連載】聞こえの衰え、見過ごしていませんか?~ヒアリングフレイルを正しく知り、豊かな人生を~
第3回:聞こえの低下が招く、社会的な孤立と孤独
お盆も過ぎ、賑やかだった夏の集いが一段落する頃。ふと訪れる静寂の中で、大切な人とのコミュニケーションの質について、改めて思いを馳せてみてはいかがでしょうか。何気ない会話のキャッチボールが、実は彼らの心と体の健康を守る上で、私たちが想像する以上に重要な役割を果たしているのです。
「聞こえない」から「関わらない」への悪循環
聴力の低下は、単に音が聞こえにくくなるという物理的な問題に留まりません。その最大の弊害は、人との繋がりを蝕んでいく点にあります。会話の内容が聞き取れないと、何度も聞き返すことに気兼ねしたり、的外れな返事をしてしまうことを恐れたりするようになります。その結果、会話に参加すること自体が苦痛になり、次第に友人との集いや趣味のサークル、地域の活動から足が遠のいてしまうのです 。
このプロセスは、当事者に深刻な心理的負担を強います。日本ウェルリビング推進機構が2023年に行った調査によれば、難聴を自覚している人の約6割(59.1%)が「家族や周囲の人に迷惑を掛けていると感じる」と回答し、同様に約6割(59.7%)が「日常生活にストレスや孤独感を感じる」と答えています 3。この数値は、聞こえないこと自体の不便さ以上に、人間関係における負い目や疎外感が、いかに大きな苦痛となっているかを物語っています。こうして、物理的な「聞こえにくさ」は、心理的な「関わりにくさ」へと転化し、人を社会的な孤立へと追い込んでいくのです。
孤独感が引き金となる健康リスク:最新研究からの警告
この「社会的孤立」や「孤独感」が、単なる気分の問題ではなく、要介護状態という深刻な健康リスクに直結することが、最新の研究で明らかになってきました。2023年4月、国立長寿医療研究センター(NCGG)の研究グループは、医学界に大きなインパクトを与える研究成果を発表しました 。
この研究は、地域在住の高齢者約4,700人を追跡調査したもので、いくつかの重要な事実を明らかにしました。
- まず、聴力低下のある高齢者(調査対象の20%)は、聴力低下のない高齢者に比べて、2年以内に要介護状態になる割合が約1.8倍も高いことが示されました(聴力低下群 8.3% vs 正常群 4.5%)。
- そして、さらに踏み込んだ分析で、この研究の最も重要な発見がもたらされました。聴力低下のあるグループに限定して見ると、「孤独感を感じている」人は、感じていない人に比べて、要介護状態になるリスクが約1.7倍に跳ね上がったのです。
- 驚くべきことに、聴力が正常なグループでは、孤独感の有無と要介護の発生率との間に、統計的に意味のある関連は見られませんでした 4。
この結果が示唆することは極めて重要です。聴力低下が健康悪化を招く主要な経路は、感覚器の障害そのものよりも、それが引き起こす「孤独感」という心理社会的な要因にある可能性が高い、ということです。つまり、「聴力低下 → 孤独感 → 要介護状態」という負の連鎖が存在することが、大規模なデータによって示されたのです。これは、今後の介護予防戦略において、単に聞こえを補うだけでなく、「孤独感をいかに防ぐか」という視点が不可欠であることを強く示唆しています。
※本コラムは、Googleの生成AI「Gemini」の支援を受けて作成され、ユニバーサルサウンドデザイン株式会社・聴脳科学総合研究所が監修しました。