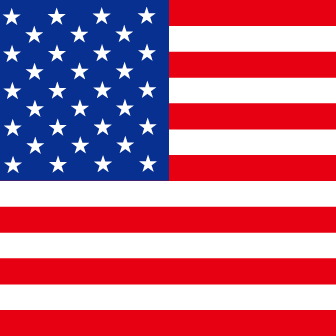[コラム]”聞こえ”と”脳”の深い関係~認知症の最大のリスク因子としての難聴~
目次
【連載】聞こえの衰え、見過ごしていませんか?~ヒアリングフレイルを正しく知り、豊かな人生を~
第4回:“聞こえ”と”脳”の深い関係~認知症の最大のリスク因子としての難聴~
夏の終わり、少しずつ秋の気配を感じる季節です。今回は、私たちの「聞こえ」と「脳の健康」、特に多くの人が関心を寄せる「認知症」との間に存在する、驚くほど深く、そして無視できない関係について、最新の科学的知見をもとに探求していきましょう。
ランセット委員会の衝撃的な報告
2020年、世界で最も権威のある医学雑誌の一つである『The Lancet』の国際委員会は、認知症予防に関する包括的な報告書を発表しました。その中で、認知症の発症リスクを高める12の「予防可能なリスク因子」が挙げられましたが、その中で最大の割合(8%)を占めたのが、中年期(45~65歳)の「難聴」でした 。これは、高血圧(5%)、過度の飲酒(1%)、肥満(1%)、喫煙(5%)といった、これまで広く知られてきた他の多くのリスク因子を上回る、極めて大きなインパクトを持つものです 。
なぜ聞こえの低下が脳に影響するのか?3つの仮説
では、なぜ耳の機能である「聞こえ」の低下が、脳の病気である認知症とこれほど強く関連するのでしょうか。専門家の間では、主に3つの仮説が議論されています 。
- 認知負荷仮説 (Cognitive Load Hypothesis): 音声情報が不鮮明な形で脳に届くと、脳はそれを理解しようと懸命に努力します。この「聞き取り」という作業に脳のエネルギー(認知リソース)を過剰に費やしてしまうため、本来、記憶や思考、判断といった他の高度な認知機能に割り当てられるべきリソースが枯渇してしまう、という考え方です。脳が常に聞き取り作業で「手一杯」になってしまうイメージです。
- カスケード仮説 (Cascade Hypothesis): これは、第3回で触れた社会的孤立と関連する仮説です。聴力低下がコミュニケーションの障壁となり、社会的な交流や知的な活動から遠ざかります。その結果、脳への刺激が慢性的に減少し、うつ状態や社会的な孤立を招きます。この刺激不足が、脳の神経回路の不使用による萎縮(use-it-or-lose-it)を引き起こし、認知機能の低下につながるという、ドミノ倒しのような連鎖反応(カスケード)を想定するものです。
- 共通原因仮説 (Common Cause Hypothesis): 聴力低下と認知機能低下は、直接的な因果関係ではなく、加齢に伴う神経系の変性や、糖尿病・高血圧といった生活習慣病による微小な血管の障害など、両者に共通する第3の要因(共通原因)によって引き起こされる、という考え方です。
脳に起きる物理的な変化
これらの仮説は、単なる推論ではありません。近年の研究は、難聴者の脳に物理的な変化が起きていることを示唆しています。国立長寿医療研究センターの耳鼻咽喉科医長である内田育恵氏らの研究グループは、日本の地域在住高齢者を対象とした調査で、難聴のある人は、ない人に比べて、記憶を司る脳の重要な部位である「海馬」の容積が有意に小さいことを報告しました 6。
さらに、アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイドβやリン酸化タウといったタンパク質との関連も指摘されています。動物実験では、騒音によって難聴を誘発すると、海馬でリン酸化タウが増加することが報告されており、また、加齢性難聴のある人では、脳脊髄液中のこれらのバイオマーカー値が上昇するとの報告もあります 。
これらの科学的証拠を総合すると、難聴は脳に対して「リソースの浪費(認知負荷)」、「刺激の枯渇(社会的孤立)」、そして「構造的な萎縮(海馬の縮小)」という、いわば三重の攻撃を仕掛ける、脳の健康にとって静かなる脅威であると言えます。聞こえの問題は、もはや耳だけの問題ではなく、脳の健康問題そのものであるという認識が不可欠です。
ただし、公平を期すために付け加えると、現時点では、補聴器などの聴覚介入が認知機能低下の進行を明確に抑制するという最高レベルの証拠(ランダム化比較試験による証明)は、まだ確立されていません 。しかし、多くの観察研究では一貫して強い関連が示されており 、聴覚への介入が認知症予防の有望な戦略となりうるという期待は、世界中の研究者の間で高まっています。
※本コラムは、Googleの生成AI「Gemini」の支援を受けて作成され、ユニバーサルサウンドデザイン株式会社・聴脳科学総合研究所が監修しました。