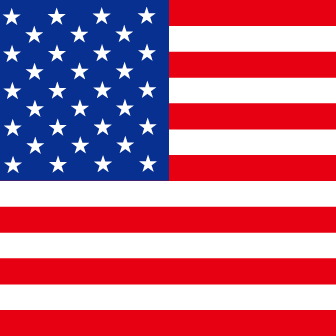[コラム]今日から始める「耳にやさしい生活」~ヒアリングフレイルの予防と対策~
目次
【連載】聞こえの衰え、見過ごしていませんか?~ヒアリングフレイルを正しく知り、豊かな人生を~
第5回:今日から始める「耳にやさしい生活」~ヒアリングフレイルの予防と対策~
9月1日は「防災の日」。この日、多くの地域で防災訓練が行われ、防災行政無線から大切な情報が流れます。その声がしっかりと届くためにも、日頃から「耳の健康」を意識することが大切です。日々の少しの心がけが、未来の豊かな聞こえを守り、人生の楽しみを広げることに繋がります。
耳への直接的な負担を減らす
ヒアリングフレイルの予防でまず大切なのは、耳への過剰な負担を避けることです。特に、大きな音に長時間さらされることは、聴覚細胞を傷つける大きな原因となります。世界保健機関(WHO)は、耳の安全を守るための具体的な基準として、大人は80デシベル(dB)以下の音量を1週間に最大40時間まで、子どもは75dB以下を同じく週40時間までと推奨しています 。
日常生活でできる「耳にやさしい生活」のポイントは以下の通りです 。
- テレビや音楽の音量を上げすぎない: 家族に「音が大きい」と指摘されたら、素直に耳を傾けましょう。遮音性の高いヘッドホンやイヤホンを使うことも、音量を上げすぎない工夫の一つです 。
- 騒がしい場所を避ける: 工事現場の近くや、大音量の音楽が流れる店舗など、大きな音が常時出ている場所には長居しないようにしましょう。
- 騒音下での作業では耳栓を: 仕事などで騒音環境が避けられない場合は、必ず適切な耳栓やイヤーマフなどの聴覚保護具を使用しましょう。
- 耳を休ませる時間を作る: 1時間に10分程度は静かな場所で過ごし、耳をリラックスさせる時間を持つことが推奨されています 。
全身の健康が、耳の健康につながる
加齢性難聴の進行を遅らせるためには、全身のアンチエイジングが非常に重要です。耳の奥で音を感じ取る「蝸牛(かぎゅう)」は、非常に繊細な器官で、たくさんの毛細血管によって栄養や酸素が供給されています。そのため、全身の血流を良好に保つことが、聞こえの健康を維持することに直結します。
具体的には、以下のような生活習慣の見直しが推奨されています 。
- 生活習慣病の管理: 高血圧や糖尿病、脂質異常症は、全身の血管にダメージを与え、耳への血流も悪化させます。かかりつけ医の指導のもと、適切に管理しましょう。
- 栄養バランスの取れた食事: 特定の食品が耳に良いというよりは、バランスの取れた食生活で血管を健康に保つことが基本です。
- 適度な運動: ウォーキングなどの有酸素運動は、全身の血行を促進します。
- 質の良い睡眠と休養: 過労やストレスは、聴覚機能にも悪影響を及ぼす可能性があります 。
- 禁煙: 喫煙は血管を収縮させ、血流を悪化させる最大の要因の一つです。
これらの予防策は、心臓病やがん、一般的なフレイル予防のために推奨される項目とほぼ同じです。つまり、「聴覚ケア」は何か特別なことではなく、質の高い生活を目指す「全身の健康管理」そのものの一部なのです。「健康的な生活を送ることが、結果的に耳も守ってくれる」という視点は、日々の生活の中に聴覚ケアを自然に取り入れる助けとなるでしょう。
手軽にできるセルフケア「側頭筋ほぐし」
一部の自治体では、耳周りの血行を促進するための簡単なマッサージも紹介されています。リラックスしたい時に試してみてはいかがでしょうか。
- 人差し指と中指でこめかみを押さえ、円を描くように優しくマッサージします(10回程度)。
- 同様に、耳の真上の側頭部をマッサージします(10回程度)。
- 耳の後ろの髪の生え際から、うなじに向かって少しずつ場所をずらしながら、3箇所ほどをマッサージします(各10回程度)。
※本コラムは、Googleの生成AI「Gemini」の支援を受けて作成され、ユニバーサルサウンドデザイン株式会社・聴脳科学総合研究所が監修しました。