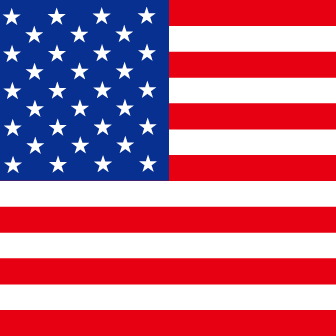[コラム]聞こえに不安を感じたら、まずどこへ?~耳鼻咽喉科と補聴器相談医の役割~
目次
【連載】聞こえの衰え、見過ごしていませんか?~ヒアリングフレイルを正しく知り、豊かな人生を~
第6回:聞こえに不安を感じたら、まずどこへ?~耳鼻咽喉科と補聴器相談医の役割~
朝晩に涼しい風が吹き、秋の訪れを感じる頃となりました。体の定期健診と同じように、「聞こえのチェック」も大切です。もし、ご自身やご家族の「聞こえにくさ」に気づいた時、自己判断で「年のせい」と放置したり、あるいはインターネットの広告を見ていきなり集音器や補聴器を注文したりするのは、最善の策とは言えません。解決への最短かつ最も確実なルートは、正しい専門家の扉を叩くことから始まります。
第一歩は必ず「耳鼻咽喉科」の受診から
聞こえにくさを感じたら、まず向かうべきは「耳鼻咽喉科」です。その理由は、聞こえにくさの原因が、必ずしも加齢だけとは限らないからです 。
- 治療可能な病気の可能性: 耳垢が固まって耳の穴を塞いでいる「耳垢栓塞(じこうせんそく)」や、中耳に液体が溜まる「滲出性中耳炎」など、簡単な処置や投薬、手術などで聴力が回復する病気は少なくありません 。
- 正確な診断の重要性: 聴力検査(純音聴力検査、語音聴力検査など)を行い、どの高さの音が、どの程度聞こえにくいのかを正確に把握することが、あらゆる対策の出発点となります。自己判断では、適切な対応はできません。
まずは耳鼻咽喉科医による医学的な診断を受け、治療可能な原因がないかを確認し、自分の聴力の状態を客観的に知ることが不可欠です。
「補聴器相談医」という頼れる専門家
耳鼻咽喉科医の中でも、特に補聴器に関する深い知識と経験を持つ専門家がいることをご存知でしょうか。それが、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が、所定の講習会の受講などを通じて認定する「補聴器相談医」です 9。
補聴器相談医は、単に補聴器が必要かどうかを判断するだけではありません。
- 患者さんの聴力の状態、生活スタイル、聞こえに困っている具体的な場面などを総合的に判断し、補聴器の適応を決定します。
- どのような種類の補聴器が望ましいかについて、専門的な指導を行います。
- 後述する「認定補聴器技能者」と連携し、補聴器の適切な調整(フィッティング)や使用訓練が円滑に進むよう、医学的な立場からサポートします。
- 補聴器購入後も、定期的に聴力の変化をチェックし、アフターフォローを行います 。
つまり、補聴器相談医は、診断から治療、そして補聴器を用いた「聞こえのリハビリテーション」全体を見守る、まさに聴覚ケアの司令塔とも言える存在なのです。
理想的な聞こえのサポート体制
国や自治体の報告書でも、この補聴器相談医や、補聴器の調整を専門に行う「認定補聴器技能者」といった専門家の存在を市民に広く周知し、彼らが連携する体制を地域に構築することの重要性が繰り返し指摘されています 10。
一般の消費者は「聞こえが悪い → 補聴器を買う」という直線的なルートを考えがちですが、日本の制度が目指す理想的な流れは、専門家が連携する「チームアプローチ」です。
- 耳鼻咽喉科医(特に補聴器相談医): 医学的診断と、補聴器適応の判断・指導
- 認定補聴器技能者・認定補聴器専門店: 具体的な機種選定、精密な調整、使用訓練、メンテナンス
この「専門家リレー」の仕組みを理解することが、情報不足によるドロップアウトや、自分に合わない製品の購入による失敗を防ぎ、効果的な聴覚ケアを実現するための成功の鍵となります。お近くの補聴器相談医は、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会のウェブサイトで検索することができます。
※本コラムは、Googleの生成AI「Gemini」の支援を受けて作成され、ユニバーサルサウンドデザイン株式会社・聴脳科学総合研究所が監修しました。