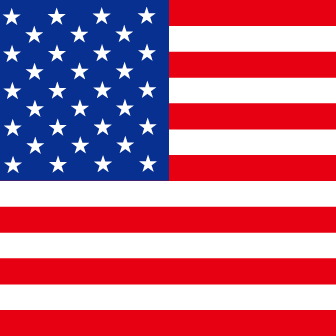[コラム]補聴器の正しい理解~「医療機器」としての役割と選び方~
目次
【連載】聞こえの衰え、見過ごしていませんか?~ヒアリングフレイルを正しく知り、豊かな人生を~
第7回:補聴器の正しい理解~「医療機器」としての役割と選び方~
本日は「敬老の日」。長寿を祝い、感謝を伝えるこの日に、高齢の親や祖父母とのコミュニケーションを支える代表的なツールである「補聴器」について、しばしば誤解されがちなその本質を、深く掘り下げていきましょう。
補聴器は「家電」ではなく「医療機器」
まず理解すべき最も重要な点は、補聴器はテレビや音響製品のような「家電」ではなく、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称:薬機法)に基づき、その品質、有効性、安全性が国によって厳しく管理された「管理医療機器」であるということです。
これは、補聴器が人体に直接影響を与える機器であり、その製造や販売には国の厳しい基準が課せられていることを意味します。誰でも自由に「補聴器」と名乗る製品を作ったり、販売したりすることはできません。この事実は、補聴器が単なる音の増幅装置ではなく、聴覚を改善するという医療的な目的を持つ、信頼性の高い機器であることを保証しています。
「補聴器」と「集音器」の決定的違い
消費者が最も混同しやすく、またトラブルの原因ともなりやすいのが、「補聴器」と、通信販売や家電量販店でよく見かける「集音器」との違いです。両者は見た目が似ているものもありますが、その本質は全く異なります。
| 比較項目 | 補聴器 | 集音器 |
| 法的分類 | 管理医療機器 | 家電製品・音響機器 |
| 主な機能 | 聞こえにくい周波数の音を選択的に増幅し、言葉の明瞭度を改善する。騒音抑制やハウリング防止など、多様な機能を持つ 。 | 周囲の音を区別なく、一律に大きくする。 |
| 調整(フィッティング) | 個人の聴力データに基づき、専門家(認定補聴器技能者など)が精密な調整を行うことが必須。 | 原則として調整機能はなく、利用者が音量を変えるのみ。 |
| 主な販売場所 | 専門家が在籍する補聴器専門店、眼鏡店などでの対面販売。 | 通信販売、インターネット、家電量販店など。 |
| 価格帯 | 片耳で数万円から50万円以上。専門家による調整・サポート費用が含まれる。 | 数千円から数万円程度。 |
| 公的助成の対象 | 障害者総合支援法や、多くの自治体の助成制度の対象となる。 | 対象外。 |
| アフターケア | 定期的なメンテナンス、再調整、相談など、長期的なサポート体制が整っている。 | 基本的にない場合が多い。 |
出典: 各種専門サイトの情報を基に作成
安価な集音器を試して効果が得られず、「補聴器は役に立たない」と諦めてしまうケースは後を絶ちません。しかし、それは適切な医療機器を、適切な専門家のもとで試していない結果である可能性が高いのです。
補聴器は「買って終わり」ではない
補聴器の効果を最大限に引き出すためには、購入後のプロセスが極めて重要です。補聴器は、装着したその日から魔法のように全てが聞こえるようになるわけではありません。むしろ、そこが「聞こえのリハビリテーション」のスタート地点です 。
長年、静かな世界に慣れていた脳にとって、補聴器を通して入ってくる様々な音は、最初は「うるさい雑音」に感じられることもあります。脳が再び音のある環境に適応し、必要な音と言葉を選び取れるようになるまでには、一般的に3ヶ月程度のトレーニング期間が必要とされています。この期間、専門家と相談しながら微調整を繰り返し、徐々に装用時間を延ばしていくことが成功の鍵です。
消費者は補聴器を高価だと感じがちですが、その価格は単にデバイス本体の代金だけではありません。そこには、購入前の詳細なカウンセリング、聴力測定、個々に合わせた精密なフィッティング、使用方法の指導、そして購入後の長期にわたる定期的な調整や相談といった、一連の専門的な「聴覚リハビリテーション・サービス」の対価が含まれているのです 16。この視点を持つことが、補聴器の価値を正しく理解し、安易な価格比較による失敗を避けるために不可欠です。
※本コラムは、Googleの生成AI「Gemini」の支援を受けて作成され、ユニバーサルサウンドデザイン株式会社・聴脳科学総合研究所が監修しました。