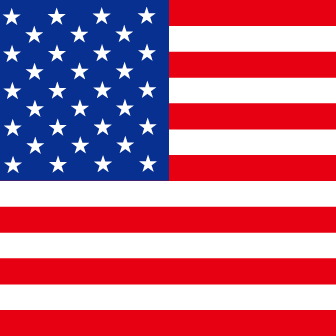[コラム]聞こえを支える、もう一つの選択肢~対話支援機器というソリューション~
目次
【連載】聞こえの衰え、見過ごしていませんか?~ヒアリングフレイルを正しく知り、豊かな人生を~
第8回:聞こえを支える、もう一つの選択肢~対話支援機器というソリューション~
秋分の日を明日に控え、昼と夜の長さがほぼ同じになるこの時期、心穏やかに過ごしたいものです。しかし、「補聴器がどうしても合わない」「特定の場面でもっとクリアに聞こえるサポートが欲しい」といった声に応えるため、近年、新しい発想の支援ツールが登場しています。今回は、メーカーの立場に依らず公平な視点から、聞こえを支えるもう一つの選択肢、「対話支援機器」というソリューションをご紹介します。
補聴器だけではない、多様な聞こえの支援
これまでの聴覚ケアは、主に「聞こえにくい人(聴者)」の耳に装着する補聴器が中心でした。しかし、対話支援機器は、そのアプローチを拡張します。これらの機器は、個人の聴力を補うだけでなく、「話者と聴者の間のコミュニケーション環境」そのものを改善することを目指しています。問題は「Aさんの耳が悪い」ことだけにあるのではなく、「AさんとBさんの間の意思疎通がうまくいかない」ことにある、と捉え直すのです。この発想の転換により、支援の担い手は難聴者本人だけでなく、その家族、介護者、施設の職員、企業の窓口担当者など、コミュニケーションの相手側にも広がります。
主な対話支援機器の種類と特徴
現在、様々な技術を用いた対話支援機器が開発・販売されています。ここでは、その代表的なカテゴリーと、それぞれの特徴、そして最適な利用シーンをまとめました。
| 種類 | 特徴 | 最適な利用シーン |
| 卓上型対話支援スピーカー | 話し手がマイクに向かって話すと、その音声が聞き取りやすい音質に変換され、スピーカーからクリアに再生される。音のバリアフリーを実現する機器 。 | 家族との食卓での会話、病院の診察室、役所の窓口、介護施設でのコミュニケーション、企業の受付など、1対1や少人数での対面会話。 |
| 音声認識文字起こしアプリ | スマートフォンやタブレットのマイクが拾った音声を、AIがリアルタイムで認識し、画面上に文字として表示する。会話の「見える化」 19。 | 騒がしい場所での会話、筆談の代わり、会議や講義内容の補助的記録、聞き間違いの確認など。聴覚障害者と健聴者のコミュニケーションツールとして開発されたものも多い 。 |
| 骨伝導ヘッドホン/イヤホン | 鼓膜を介さず、骨の振動によって直接、内耳に音を伝える。耳の穴を塞がないため、周囲の音も同時に聞くことができる。 | 周囲の安全を確認しながら音楽やナビゲーション音声を聞きたいランニング時や、軽度の伝音難聴の方、家族と一緒にテレビを観る際に手元スピーカーとして利用するなど。 |
エビデンスに基づく効果
これらの機器は、単なる便利なガジェットというだけではありません。その有効性を示す科学的なエビデンスも報告され始めています。例えば、徳島大学病院で行われた研究では、卓上型の対話支援機器を認知症患者とのコミュニケーションに利用した結果、患者の興奮や不安といった認知症に伴う行動・心理症状(BPSD)や、生活の質(QOL)が改善する可能性が示唆されました 21。これは、クリアなコミュニケーションが、患者の心理的な安定に繋がり、看護介入時の負担軽減にも貢献することを示しています。
このように、「聞こえの支援」は、個人の耳に装着するデバイス中心のアプローチから、コミュニケーションが行われる「場」そのものをデザインする、よりユニバーサルな環境ソリューションへと進化・拡張しています。自分の生活シーンや困りごとに合わせて、補聴器とこれらの対話支援機器を賢く使い分ける、あるいは併用することで、より快適なコミュニケーションを実現できる可能性があるのです。
※本コラムは、Googleの生成AI「Gemini」の支援を受けて作成され、ユニバーサルサウンドデザイン株式会社・聴脳科学総合研究所が監修しました。