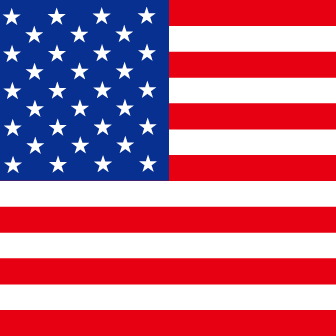[コラム]国の支援制度を知る~障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度~
目次
【連載】聞こえの衰え、見過ごしていませんか?~ヒアリングフレイルを正しく知り、豊かな人生を~
第9回:国の支援制度を知る~障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度~
9月も終わりに近づき、来年度の公的な手続きについて考える機会も出てくる頃でしょう。今回は、聞こえの問題を抱える人々にとって最も基本的なセーフティネットである、国の公的支援制度について解説します。特に、補聴器の購入に関して、どのような人が、どのような支援を受けられるのか、その仕組みと対象者を正しく理解しましょう。
障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度
日本において、補聴器購入に対する最も根幹となる公적支援制度は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(通称:障害者総合支援法)」に基づく「補装具費支給制度」です 22。
この制度は、身体に障害のある人々が、その障害を補い、日常生活や社会生活を送りやすくするための用具(補装具)の購入や修理にかかる費用を支給するものです。補聴器もこの補装具の一つとして位置づけられています。原則として、購入や修理にかかる費用の1割が自己負担となり、残りの9割が公費(国、都道府県、市町村が負担)で賄われます。ただし、世帯の所得に応じて自己負担額には月額の上限が設けられています 22。
誰が対象になるのか?
この制度を利用するためには、前提として「身体障害者手帳(聴覚障害)」の交付を受けている必要があります。では、どのような聴力レベルの人が手帳の交付対象となるのでしょうか。
身体障害者福祉法で定められている聴覚障害の等級は、最も軽度な「6級」から最も重度な「2級」まであります。そのうち、最も軽度である6級の基準でさえ、以下のいずれかに該当する必要があります 24。
- 両耳の聴力レベルが70デシベル(dB)以上のもの (40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
- 一側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの
70dBの難聴とは、WHO(世界保健機関)の基準では「準重度難聴(Severe hearing loss)」から「重度難聴」に分類され、耳元で大声で話されないと会話が理解できないレベルです 。つまり、この国の制度は、かなり進行した高度な難聴を持つ人々を対象としていることがわかります。
制度の「隙間」にいる多くの高齢者
一方で、WHOの基準では、聴力レベルが41dBから55dBの範囲は「中等度難聴(Moderate hearing loss)」とされ、この段階でも「普通の会話が聞き取りにくい」状態です 。日常生活や社会参加において、すでに大きな不便を感じているにもかかわらず、身体障害者手帳の交付基準には満たない。こうした「中等度難聴」の高齢者が、実は非常に多く存在します。彼らは、国の制度の対象外、いわば「制度の隙間」に置かれているのが現状です。
この現実は、データによっても裏付けられています。一般社団法人日本補聴器工業会が実施した大規模調査「JapanTrak 2022」によると、実際に補聴器を所有している人のうち、障害者総合支援法や後述する自治体独自の制度など、何らかの公的助成を受けて購入したのは、わずか8%に過ぎませんでした 。
この事実は、国の支援制度を批判するものではありません。障害者総合支援法は、その名の通り「障害福祉」の枠組みであり、一定以上の障害を持つ人々の社会参加を支えるという明確な目的を持っています。しかし、ヒアリングフレイル対策が目指す「加齢に伴う聞こえの衰えを早期に捉え、フレイルや認知症への進行を予防する」という「公衆衛生・介護予防」の観点とは、その目的と対象が異なります。この制度設計上の目的の違いが、多くの支援を必要とする高齢者が公的サポートを受けられないという「制度的ギャップ」を生み出しているのです。このギャップを埋めるために、次にご紹介する「自治体独自の取り組み」が、今、極めて重要な役割を担っています。
※本コラムは、Googleの生成AI「Gemini」の支援を受けて作成され、ユニバーサルサウンドデザイン株式会社・聴脳科学総合研究所が監修しました。