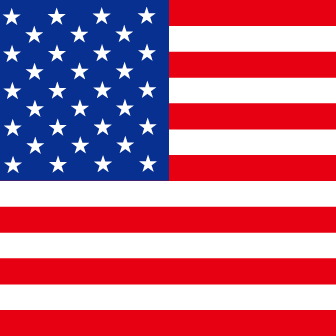[コラム]広がる自治体の支援の輪~高齢者向け補聴器購入費助成の先進事例~
目次
【連載】聞こえの衰え、見過ごしていませんか?~ヒアリングフレイルを正しく知り、豊かな人生を~
第10回:広がる自治体の支援の輪~高齢者向け補聴器購入費助成の先進事例~
10月に入り、過ごしやすい気候となりました。前回のコラムで明らかになった、国の制度ではカバーしきれない「聞こえの悩み」に対し、地域社会が独自に手を差し伸べる動きが、今、全国の市区町村で着実に広がっています。
自治体が動く理由
なぜ、多くの自治体が独自の予算を投じてまで、高齢者の補聴器購入を支援するのでしょうか。その背景には、ヒアリングフレイル対策が、単なる個人のQOL向上に留まらない、より大きな社会的利益をもたらすという認識があります。
- 国の制度の補完: 障害者手帳の対象とならない中等度難聴の高齢者が、支援から取り残されているという「制度的ギャップ」を埋めるため 24。
- 介護予防・認知症予防への投資: これまでのコラムで見てきたように、難聴は社会的孤立や認知症の強力なリスク因子です。早期に補聴器の使用を促すことで、将来の認知症発症を予防し、健康寿命を延伸することは、結果として将来の医療費や介護給付費の増大を抑制することに繋がります。これは、地域社会にとって極めて費用対効果の高い「未来への投資」なのです 25。
先進的な自治体の取り組み
全国で広がる助成制度ですが、その内容は自治体によって様々です。ここでは、特に先進的で、他の自治体のモデルともなりうる3つの事例をピックアップし、その特徴を比較してみましょう。
| 比較項目 | 東京都 港区 26 | 新潟県 三条市 | 北海道 北広島市 29 |
| 主な目的 | 高齢者の生活支援及び社会参加の促進 | 難聴による認知症予防 | 介護予防や認知機能低下を予防し、積極的な社会参加を促す |
| 対象年齢 | 60歳以上 | 50歳以上 | 65歳以上 |
| 聴力要件 | 特になし(補聴器相談医が必要と認めること) | 片耳の聴力レベルが40dB以上、又は医師が必要と認めること | 身体障害者手帳の交付対象とならないこと(中等度難聴が主対象) |
| 助成上限額 | 144,900円(住民税課税世帯は72,450円) | 50,000円(住民税課税世帯は25,000円) | 50,000円(購入費用の1/2) |
| 主な条件 | ・補聴器相談医の診断が必須 ・認定補聴器技能者が在籍する店舗での購入が必須 | ・医師による補聴器購入意見書が必須 ・認定補聴器技能者による適合調整と1週間以上の試聴が必須 | ・補聴器相談医による意見書が必須 |
これらの先進的な自治体の制度設計を詳しく見ると、単にお金を支給するだけの「購入補助」ではないことが分かります。港区、三条市、北広島市のいずれも、「補聴器相談医」や「認定補聴器技能者」といった専門家の関与を助成の必須条件としています。これは、助成金をインセンティブとして活用し、高齢者を闇雲な自己流の対策ではなく、第6回で解説した「医師と専門家が連携する、理想的な聴覚ケアのループ」へと正しく導こうとする、極めて戦略的な「公衆衛生プログラム」としてデザインされているのです。
これらの自治体は、ヒアリングフレイルと認知症・介護の関連性という科学的エビデンスに基づき、地域レベルで実践的な社会システムを構築しています。ご自身の住む街の制度はどうなっているか、ぜひ一度、市区町村の高齢者福祉担当課や地域包括支援センターに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
※本コラムは、Googleの生成AI「Gemini」の支援を受けて作成され、株式会社聴脳科学総合研究所が監修しました。