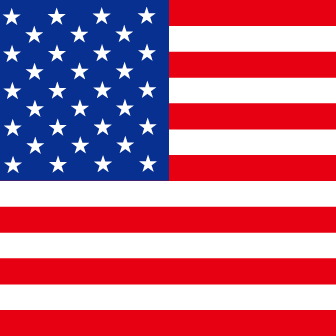[コラム]家族や地域社会にできること~聞こえにくい人とのコミュニケーションのコツ~
目次
【連載】聞こえの衰え、見過ごしていませんか?~ヒアリングフレイルを正しく知り、豊かな人生を~
第11回:家族や地域社会にできること~聞こえにくい人とのコミュニケーションのコツ~
今日は「スポーツの日」。体を動かす心地よさと同じくらい、心と心の通った豊かな対話も、私たちの健康にとって欠かせません。特別な機器や制度だけでなく、私たち一人ひとりの少しの心がけが、聞こえにくい人とのコミュニケーションを大きく改善する力になります。
「大きな声」より「分かりやすい声」
聞こえにくい人に対して、私たちはつい大声で、時には怒鳴るように話してしまいがちです。しかし、これは多くの場合、逆効果です。特に加齢性難聴では、単に音が小さく聞こえるだけでなく、音の周波数のバランスが崩れ、言葉の輪郭がぼやけて聞こえる「音の歪み」を伴います。特に、子音などの高い周波数の音が聞き取りにくくなるため、大声で話すと音が割れてしまい、かえって聞き取りにくくなるのです 32。
大切なのは「声量」よりも「明瞭さ」です。以下に、今日から実践できるコミュニケーションのコツを挙げます。
- 正面から、顔を見せて話す: 口の動きや表情といった視覚情報が、言葉の理解を大きく助けます。
- 少しゆっくり、はっきりと話す: 早口は禁物です。一語一語を区切るように、落ち着いたトーンで話しましょう。
- 言い方を変えてみる: 聞き返された時に、全く同じ言葉を同じ声量で繰り返すのは得策ではありません。「明日の9時に駅前で」が伝わらなければ、「朝の9時、駅の改札の前だよ」というように、別の言葉で言い換えてみましょう。
- 会話の前に注意を引く: いきなり話し始めるのではなく、「おじいちゃん」と名前を呼んだり、肩を軽く叩いたりして、相手の注意をこちらに向けてから話し始めましょう。
- 周囲の雑音を減らす: 会話の際は、テレビやラジオを消す、騒がしい場所を避けるなど、できるだけ静かな環境を整えることが重要です。
お互いの心理的負担を理解する
コミュニケーションの困難は、技術的な問題だけではありません。そこには、双方の心理的な壁が存在します。
聞こえにくい本人は、「何度も聞き返すのは申し訳ない」「周りの会話の邪魔をしているのではないか」という負い目を感じています 3。その結果、分かったふりをして曖昧に頷いたり、会話に参加することを諦めたりしてしまいます。
一方、話す側も、善意からであっても「何度も同じことを説明するのは疲れる」「どうせ伝わらないだろう」と感じてしまうことがあります 。こうした小さなすれ違いが積み重なり、お互いの間に見えない壁を作り、コミュニケーションそのものを減らしてしまうのです。
この悪循環を断ち切る鍵は、単なる音量調整ではなく、「心理的な障壁の除去」にあります。先ほど紹介した「分かりやすく話す」という工夫は、単に情報を伝達しやすくするだけでなく、「私は、あなたにきちんと伝えたいと思っていますよ」という、思いやりと敬意のこもった非言語的なメッセージを送ることでもあります。このメッセージが、本人の「申し訳ない」という気持ちを和らげ、安心して「もう一度言ってくれる?」と聞き返せる信頼関係を再構築します。聞こえにくい人とのコミュニケーション改善は、お互いの心理的負担を軽減し、対話への意欲を再燃させるための、思いやりに満ちた共同作業なのです。
※本コラムは、Googleの生成AI「Gemini」の支援を受けて作成され、株式会社聴脳科学総合研究所が監修しました。