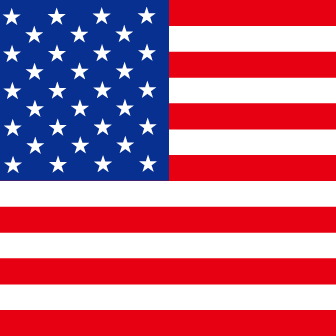[コラム]未来の聞こえのために、今、行動を~総括とこれからの展望~
目次
【連載】聞こえの衰え、見過ごしていませんか?~ヒアリングフレイルを正しく知り、豊かな人生を~
第12回:未来の聞こえのために、今、行動を~総括とこれからの展望~
秋も深まり、読書や芸術鑑賞など、静かに物思いにふけるのに良い季節となりました。この連載を通じて探求してきた「ヒアリングフレイル」の知識を力に変え、あなた自身の、そしてあなたの大切な人の豊かな人生のために、今、具体的な一歩を踏み出す時です。
連載の総括:ヒアリングフレイルという社会課題
この連載で、私たちは「ヒアリングフレイル」という概念を多角的に掘り下げてきました。改めて、その要点を振り返ってみましょう。
- ヒアリングフレイルは、単なる個人の老化現象ではありません。それは、社会的孤立 4
認知症の最大のリスク因子 、そして要介護状態への入り口 と密接に結びついた、日本の超高齢社会が直面する喫緊の公衆衛生上の課題です。 - 日本の高齢者における難聴の有病率は極めて高く、75歳以上では7割から8割に達すると報告されています 33。しかし、その一方で、対策の要となる補聴器の装用率は15%程度に留まっており 、その多くが公的支援を受けずに自己負担で購入しているという、「高いリスク」と「手薄な対策」の間に大きなギャップが存在します 。
- しかし、ヒアリングフレイルは「予防・対策が可能」な状態です。「耳にやさしい生活」から、耳鼻咽喉科医や補聴器相談医といった専門家との連携 、そして補聴器や対話支援機器 の適切な活用に至るまで、私たちが取りうる選択肢は数多く存在します。
- さらに、国の制度の隙間を埋めるべく、東京都港区や新潟県三条市のように、介護予防や認知症予防という明確なビジョンを持って、高齢者の補聴器購入を支援する先進的な自治体が増えつつあります 。
個人、そして社会への呼びかけ
ヒアリングフレイル対策は、個人の生活の質(QOL)を高めるだけに留まりません。それは、将来の医療費や介護費の増大を抑制し、社会全体の活力を維持するための、極めて費用対効果の高い「未来への投資」です。この問題が、個人の努力だけに委ねられるべきではありません。国や自治体、医療機関、そして私たち市民一人ひとりが、この問題の重要性を認識し、社会全体で取り組むべき課題として捉える必要があります。
禁煙運動や生活習慣病対策が、かつて日本の公衆衛生を大きく前進させたように、ヒアリングフレイルへの社会的関心と対策の強化は、日本の健康寿命をさらに延伸し、社会保障の持続可能性を高める上で、次なる重要なフロンティアとなり得るのです。
あなたへの最後のメッセージ:最初の一歩を踏み出そう
この長い連載を最後までお読みいただき、ありがとうございました。知識は、行動に移してこそ力となります。
もし、この連載を通じて、ご自身やご家族のことで少しでも思い当たることがあれば、まずは第2回でご紹介したセルフチェックリストを試してみてください。
そして、もし不安を感じたら、どうか勇気を出して、お近くの耳鼻咽喉科、あるいは補聴器相談医の扉を叩いてください。専門家への相談は、決して特別なことでも、恥ずかしいことでもありません。
あなたのその一歩が、ご自身や大切な家族の、未来にわたる豊かなコミュニケーションと、健やかで彩りある人生を守るための、最も確実で、最も価値ある一歩となるのですから。
※本コラムは、Googleの生成AI「Gemini」の支援を受けて作成され、株式会社聴脳科学総合研究所が監修しました。